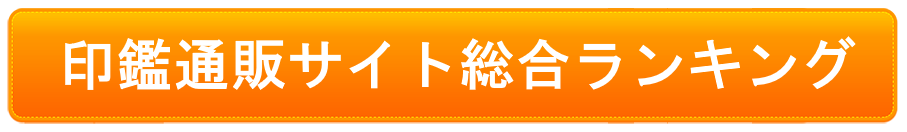| トップページ | > | 印鑑で使われる主な書体について |
印鑑で使われる主な書体について
 |
 |
こちらのページでは、印鑑で使われる主な書体について、それぞれ解説しています。
篆書体(てんしょたい)

篆書体は、とても古い書体です。
中国において、秦の時代(紀元前230年頃)に、始皇帝の指示で、
「小篆(しょうてん)」と言われる文字が出来ました。
小篆は、「大篆(だいてん)」と言われる文字が改良されて出来ましたが、
小篆の曲線部を抑えて、直線的にして、印章用にしたのが篆書体です。
篆書体は、印篆(いんてん)とも言われます。
また、篆書体の文字は縦長で、太さがほぼ一定です。
日本最古の印鑑と云われている「漢倭奴国王(かんのわのなのこくおう)」と刻まれている金印がありますが、
この金印の書体は、篆書体です。
また、日本銀行発行の紙幣に描かれている印鑑の書体は、篆書体です。
篆書体は、可読性が低く偽造されにくいです。
篆書体は、印鑑ではよく使用される書体です。

太枠篆書体(ふとわくてんしょたい)

太枠篆書体は、篆書体の印鑑の枠が、太枠になっています。
ですので、太枠篆書体の印鑑の枠は、欠けにくいです。
太枠篆書体は、ある大手通販サイトでは、女性に人気があるそうです。
印相体(いんそうたい)

印相体は、吉相体(きっそうたい)とも言われます。
印相体は、印面の中心から文字の線が上下左右斜めの八方に、末広がりになっているので、
八方篆書(はっぽうてんしょ)とも言われます。
印相体は、篆書体が元になって昭和の初期に考案された書体ですので、
歴史は浅いです。
また、印相体は縁起の良い書体と言われる場合があります。
また、印相体の特徴は、文字が枠線とくっついている点で、
印面全体を使って文字が書かれている場合が多いです。
また、印相体は文字が枠線とくっついているので、枠が欠けにくいという利点があります。
また、印相体は印影が複雑なので、可読性が篆書体よりも、さらに低いです。
しかし、実印登録をする場合に、印鑑の書体を印相体にすると、
審査に通らない場合が稀にあるそうです。
また、印相体は篆書体に次いで、よく使われる書体です。
隷書体(れいしょたい)

篆書体は、複雑で書きにくいため、篆書体を簡略したのが隷書体です。
隷書体は、中国の秦の時代から使用されていましたが、
漢の時代(紀元前206~紀元後220年)に普及しました。
隷書体は、日本銀行発行の紙幣の中の文字や、
新聞や、会社のロゴデザインなどに使われています。
また、隷書体は横長で、独特のトメとハネが特徴です。
また、隷書体は可読性が高いです。
また、隷書体は認印でよく用いられます。
古印体(こいんたい)

古印体は、隷書体と大和古印(やまとこいん)と言われる古い印鑑書体が原型となって、
7~8世紀頃に、日本で独自に作られました。
古印体は、文字の線に墨溜りや欠け途切れがあって、
丸みがあるのが特徴です。
古印体の墨溜りや欠け途切れは、鋳造物の金属にできた錆から発祥したと言われています。
また、古印体は可読性が高いです。
また、古印体は認印でよく用いられます。
行書体(ぎょうしょたい)

行書体は、楷書体を崩した書体です。
行書体は、楷書体と草書体の中間の書体として、中国で生まれました。
行書体は、現在は日本で一般的に幅広く使われています。
また、行書体は書道では、一般的な書体の1つです。
しかし、印鑑で使われることは少ないです。